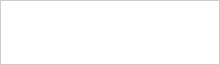第106号 我慢と忍耐
「自分でもできねえことを、くどくどと説教したって、誰も聞きゃしねえよ、それよりか、出来ねえながらも努力する姿を見せた方が、よっぽどいいと思わねえかい」…確か、ある時代小説に出てくる江戸っ子の台詞です。私はこれを読んだ時に、私に向けて言っているように感じたのでした。
まさに「雄弁は銀、沈黙は金」だとしみじみ想いました。
初めの詩は、私自身を反省して作った詩です。我慢の大切さを身にしみて感じたのです。
では読んでください。
〈我慢〉
麦は踏まれて
凛として冬を越す
フキノトウは
雪に覆われて
凍てついた大地の中で
春を待つ
紅白の梅は
寒風にさらされながら
力強く花を広げ
実を付ける
野球少年は
灼熱地獄を耐え抜いて
技を磨く
耐えることを知ってこそ
花を咲かせ
実をつけることができる
歯を食いしばって
我慢して
耐えて耐えて
耐え抜いて
未来を見据える
▽ 見えなくなってから特に我慢の必要性を感じています。「継続は力なり」とはよく言ったものですね。
ひとつのことを続ける難しさを、私だけではなく、皆さんも感じた経験はあるのではないでしょうか。
次の詩は、昭和のど真ん中で生まれた私が、昭和を懐かしみ作った詩です。
どうぞ読んでください。
〈小春日和〉
麗らかな休日
ほのぼのとした陽光
ふんわりと柔らかな風
眩しく光る蒼穹
陽だまりでじゃれ合う二匹の子犬
日向ぼっこを楽しみ
毛繕いをしている大きな三毛猫
電線に並び
羽繕いをする雀たち
もんぺを穿いて
縁側で足の爪を切る
背の曲がったおばあちゃん
田んぼ道をそぞろ歩くのは
杖をついたおじいちゃん
縄跳びで遊んでいるのは
ほっぺの赤い女の子たち
目の色を変えべいゴマをするのは
元気な男の子たち
ラジオから流れるのは
てんとう虫のサンバ
ブラウン管の中で
十六文キックをしているのは
ジャイアント馬場
昭和を懐かしむ人たちが
うっとりと歌うのは
北国の春
※ 小春日和(こはるびより):初冬に使われる言葉。冬の季語。晩秋から初冬にかけての麗らかな日を言うようです。真冬や初春に使うのは間違えていると、辞書には書いてありました。
▽ 皆さんは昭和生まれですか、平成生まれでしょうか、まさかこれを読んでくださっている方の中に令和生まれの人はいないとは想いますが…
今回も、長い詩を最後まで読んでくださりありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
石田眞人でした